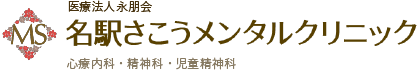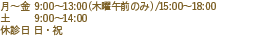高機能広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)の定義について

ブログでもなんども話題としてはでてきていますが、広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)について再度確認です。
<広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)>
まずはおさらいで、DSMでの広汎性発達障害の診断についてです。
発達障害は,精神遅滞(mental retardation),学習障害(learning disorders),運動能力障害(motor skills disorder),コミュニケーション障害(communication disorders),広汎性発達障害(pervasive developmental disorders;PDD)に分けられます。
<診断基準>
最初に国際的な診断分類によって,PDDの概念を整理します。精神医学における国際的な診断分類には,アメリカ精神医学会の診断統計マニュアル第4版(DSM-Ⅳ-TR)(American Psychiatric Association, 2000)と世界保健機関の国際疾病分類第10版(ICD-10)があり,基本的にはどちらかの診断基準に基づき日常臨床と研究は進められています。この両者は改訂を重ね,最新版では各疾患について類似した内容となっています。
<DSM-Ⅳ-TRによるPDD>
PDDは発達のいくつかの面における重症で広範な障害として特徴づけられ,DSM-Ⅳ-TRでは自閉性障害,レット障害,小児期崩壊性障害,アスペルガー障害,特定不能の広汎性発達障害(PDDNOS)に分けられています。PDDとは,①相互性対人関係の質的な問題,②コミュニケーションの質的な問題,③行動・興味の限定的,反復的で常同的な様式,の3つの領域に障害があることで特徴づけられます。
では高機能とはどういうことを指すのでしょうか。
まずは一般的な定義としては、
・「知的障害のない」広汎性発達障害
・通常はIQ>70と定義
・広汎性発達障害の診断基準にはIQは含まれていない。
・高機能者に特有の問題が存在する
上記のように定義されていることが多いと思います。
つまり高機能だから病態がいいというわけではなく、高機能であるための問題というものが生じるということが重要です。つまりIQが問題なくても、広汎性発達障害の診断はつくため、対人相互性の障害を中核としたさまざまな困りごとが生じる可能性はあります。またIQが問題ないために診断がつくのが遅れ、病院を受診する段階では広汎性発達障害による二次障害が生じてしまっているケースも少なからずあります。
大人になってから病院を受診する方は、二次障害の方を主訴に来院されていることが多いのではないかと思います。例えば、主訴としては、元気がない、食欲がない、夜ねれない、気分が落ち込んでしまう、体がだるい、頭痛、腹痛、めまい、などなど、多岐にわたります。しかしこれらの原因がPDDがあるせいで仕事や家庭、学校生活でうまくいかないことの結果として生じているのでれば、表面に見えている症状だけを治療しても、根本的な解決にはならないことになります。
大事な部分なので繰り返しますが、広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害:ASD)や注意欠如多動性障害(ADHD)の診断基準にIQは入っていないということです。つまりIQが高くても、低くてもASDやADHDの診断はつくということです。ではなぜIQを測定しているのかといえば、下位項目のばらつきをみたいのと、あまりにIQが低ければ主病態が知的障害ということになり対応の仕方は異なってくるからです。
さらにいえば発達検査をやらなくてもASD,ADHDの診断は丁寧な問診、生育歴の聴取によって可能だということです。
<「高機能」であることが意味するもの>
・広汎性発達障害としての特性が軽度とは限らない
場が読めない、冗談や皮肉が通じない、特定の興味に限局、常同性への固執、こだわり
・対人性への指向
行動の結果、相手の気持ちを見通すことができない。
低い対人スキル→不適切な対人行動の学習
・周囲からの理解・配慮が得られにくい
「わかるはずなのに」「わざとやっているのでは」
高い対人性の要求→ネガティブな経験の蓄積
・不適応状況が持続しながら、成人期に達することも多い
高機能なため、診断がつくことが遅れることで上記のような問題がおきる可能性があります。失敗体験を繰り返すことで自己評価が低下してしまい、自我機能が落ちてしまい二次障害へと発展するリスクがあります。二次障害が生じてから病院を受診する方の方が多い印象がありますが、そうなってからの治療はやはり時間がかかるため、早期に発見して早い時期からなんらかの治療的アプローチをしてあげた方がいいのだろうと思います。
あまりに失敗体験が多いと、「努力してもどうせうまくいかない」と自信のない子どもになってしまいます。
失った自信を回復するためには、現実場面での成功体験が必要となります。そのためには本人の特性に合った環境を学校や職場で調整していただくか、自らそのような環境を選択していかなれば、いつまでも失敗体験を繰り返すことになってしまいます。
<高機能広汎性発達障害の発達で忘れがちなこと>
・発達障害を持ちながら産まれ、親子関係、友人関係が展開し人格が形成されていくということ
・親に常に愛され、見守られているという安心感の感じられなさ
・子が親の愛情を常に求めていると感じられない親の不甲斐なさ
・親が何を言っても、届いているか分からない無力感
高機能ゆえの親子間の問題も生じてきます。対人相互性の障害があると母子の愛着形成を障害することがあります。つまり親からすると自分の愛情が届いていない感じがしますし、子どもからすると自分のことを理解してもらっていない、という双方向のずれが生じてしまいます。そのずれを埋めるためには広汎性発達障害という疾患概念が親、子どもの双方に必要です。親は知識をつけることで本人の感覚に近づく必要があり、本人は自分の努力だけの問題ではないと肩の荷を少しでも下す必要があります。また肩の荷をおろすのは、育て方のせいだと言われていたかもしれない親にも必要な作業をとなります。つまり発達障害の診断がつくことで、子ども、親の双方が腑に落ちる部分があることが重要だと思います。通常は互い違う部分で腑に落ちることが多いかなと思います。
やはり一番の治療者は家族(特に母親)となることも多いと思います。他者に評価される(褒められる)のおうれしいと思いますが、やはり家族の方に評価してもらうのは特別な体験かと思います。
また家族も本人への自分の接し方、対応があっているかどうか、悩むことが多いと思います。自分の心の中のもやもやを整理するために家族の方にも病院を受診していただくことは少なからずあります。家族は1つのシステムであり、誰か一人が我慢して成立している状況は本来はすでに破綻しているのではないかと思います。家族を一つのシステムととらえることで、治療的な観点からみても多面的にアプローチできるので、家族が診療の場ででてくることができるのであれば協力していただいた方がいいと思います。家族が精神的に安定することができれば、本人の治療をより保護的に、そしてスピーディーに行うことができるかもしれません。
今回は高機能広汎性発達障害について、その定義、高機能がゆえに発生する問題点、本人、家族へのアプローチの仕方について考察してみました。
もちろん一人一人性格も器質も異なりますので、高機能広汎性発達障害の方すべてに同じことが当てはまるわけではありません。
しかし基本となる知識は自分や他者を知るうえでは役に立つことがあります。それはどの疾患についても同様だと思います。
精神医学の知識とは人とは何かを追求していって生まれたものです。自分とは何かを突き詰めていくことは、人とは何かを突き詰めていくことにつながっていきます。
これからも色んな面から精神医学の情報を発信していきますので、少しでも自らの問題を解決するためのヒントになればと思って作成させていただきます。
医療法人永朋会 理事長 加藤晃司