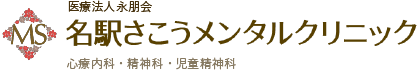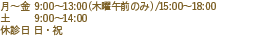うつ病、発達障害、ADHDと脳腸相関

毎日診察をしていて、気になったことを今回書きます。
うつ病、強迫性障害・不安症などストレス性障害、自閉スペクトラム症(発達障害)・注意欠如多動症など神経発達障害、
様々な疾患の方が当院に来院されますが、
しばしばお話で聞くことは、
「食事を改善したら精神症状が良くなった!」という意見です。
脳腸相関という概念があり、
脳(中枢神経系)と腸(腸内環境・腸内細菌)が互いに影響をし合う関係のことを指します。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境がメンタルヘルスや認知機能、ストレス耐性などに大きな影響を与えることが科学的に証明されています。
とはいっても、
「これを食べたらうつ病が改善した!」「ADHDが良くなった!」
など、特定の食材が治療効果を十分に持つのかというと、エビデンスはまだないです。
(魚の油に含まれるオメガ3脂肪酸は抗炎症作用をもち、うつ症状の改善に効果があるという報告はありますが、それは製剤レベルの服用量であり、サバやマグロなどを毎日食べたら効果があるのかは、わからないです。)
ちなみに効果があった!と聞くのは、
糖質制限をすることで、イライラや過食、衝動的な言動がへった!
全般的に食事を見なおすことで、(腸内の免疫系が全身の炎症反応に影響し)うつ病や不安障害など精神症状の改善につながった!
などです。
たしかに、これまでファストフード、飲酒、脂っこい食事など乱れた食生活だった方だとしたら、がらりと全般的に食生活を改善したら、精神的に安定するのは腑に落ちます。
でも、もともと一般的で普通な食生活の方も、
「パンをやめて玄米にした」
「ヨーグルト、納豆などの発酵食品を摂るようにした」
などの、変化で効果を実感されているのが興味深いです。
また、食事を見直すことで、規則正しい生活が送ることができ、丁寧に日常生活を送れることがよいと思います。
名駅さこうメンタルクリニック
院長 丹羽亮平
・子どものこころ専門医
・日本児童青年精神医学会 認定医
・日本精神神経学会認定 精神科専門医
・日本精神神経学会認定 精神科専門医制度指導医
・精神保健指定医
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
当院ホームページはこちらより
https://meiekisakomentalclinic.com
名駅さこうメンタルクリニック
〒451-0052
愛知県名古屋市西区栄生2-7-5 キョーワ調剤薬局2F
電話 : 052-551-7717
FAX : 052-551-7727